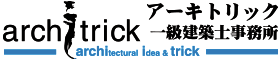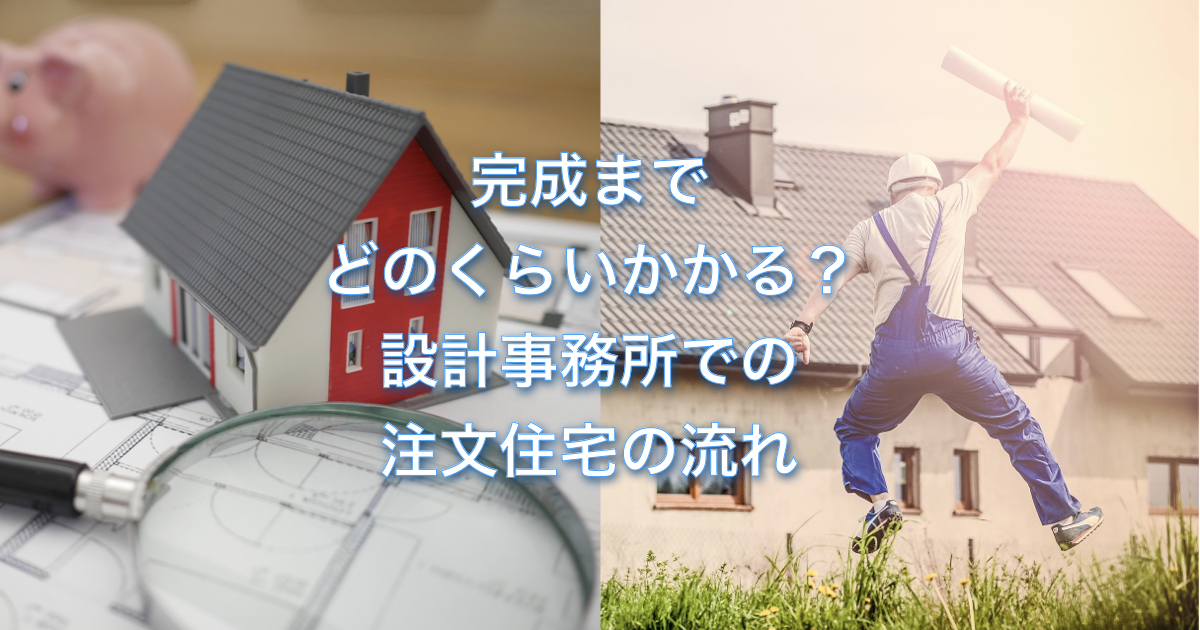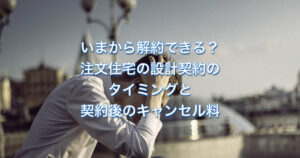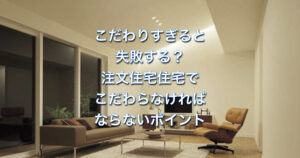基本設計と実施設計の違いって?注文住宅の設計の流れと各段階で決めるべきこと
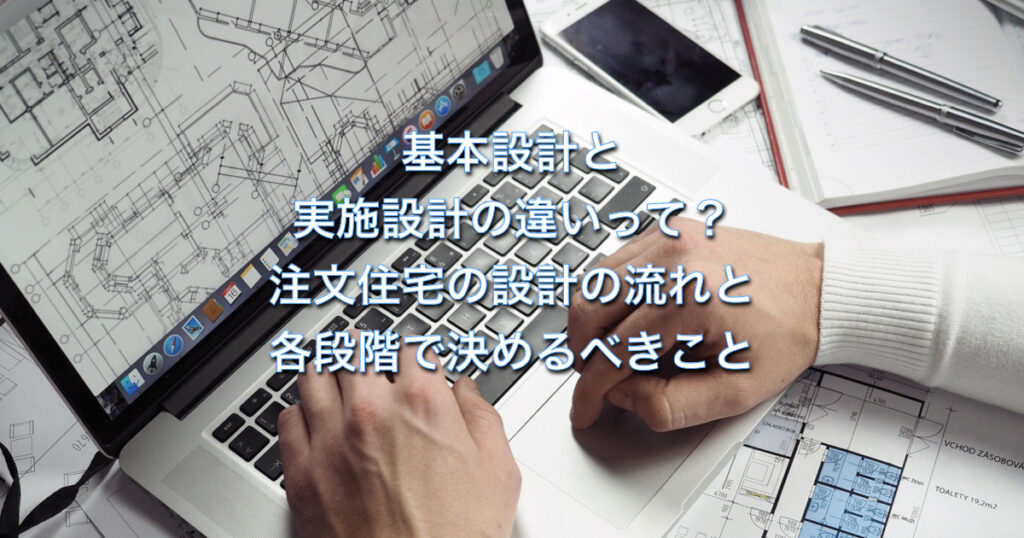
設計事務所に注文住宅を頼むと基本設計と実施設計が設計料でしっかりと分かれているのが通常です。
ハウスメーカーや工務店で設計を頼むと基本設計と実施設計の切り替わりが曖昧で特に分かれていません。

基本設計と実施設計ってどう違うの?
プラモデルで例えると、パッケージのデザインが基本設計で、パーツを組立る説明書が実施設計だとイメージしてもらうとわかりやすいかと思います。
設計事務所の注文住宅の場合は基本設計で建築基準法上での規制などをチェックして建物のボリュームや間取り、コンセプトなどを決め、
実施設計で具体的に建物を建てるための材料や設備、構造などを決めていく設計になります。
設計事務所の注文住宅では工務店やハウスメーカーのようにまだ施工会社が決まっていないので、
どのこ施工会社でも理解できるように実施設計(説明書)が必要になります。
今回は、設計事務所の注文住宅の設計の流れについてや、基本設計と実施設計でなにを決めるのかをご紹介します。
この記事で設計事務所の設計の流れでなにをすればいいのか分からないで不安に思っている人の悩みが少しでもなくなれば幸いです。
【自己紹介】

Bさん@アーキトリック
一級建築士 第303020号
耐震診断・耐震改修技術者
アーキトリック一級建築士事務所
設計事務所を18年間(2024年現在)運営している現役の一級建築士です。
店舗や旅館を中心に3桁の案件をこなしてきました。
現在は住宅設計やリノベーションを中心に活動をしています。
設計事務所のブログを始めて2年目で月間25000PVを達成!
住宅に関する悩みを解決すべく、ブログやTwitterで情報発信しています。
「いいね!」や「フォロー」していただけるとうれしいです。ヨロシク(b・ω・d)デス♪
それからコメント欄はこれまで皆さんが経験してきたことを発信する場として使っていただければ幸いです。
役立つ情報をみんなで共有できるような書き込みは大歓迎です。
基本設計と実施設計の違い
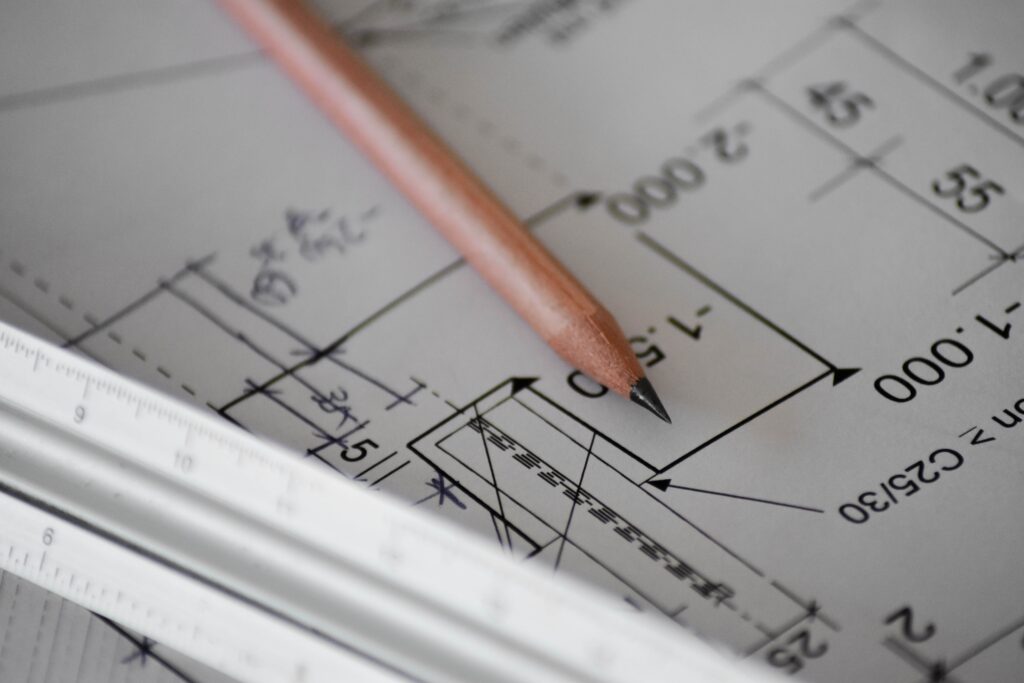
基本設計と実施設計の違いを理解するためにまずは、設計事務所の注文住宅の流れを理解しましょう。
注文住宅の設計の流れ
設計事務所の注文住宅の流れは以下のようになります。
①予算とイメージづくり
②設計事務所選び
③基本設計
④設計監理等業務委託契約
⑤実施設計
⑥相見積もりと施工会社選び
⑦見積り調整
⑧工事請負契約
⑨着工
⑩中間検査
⑪竣工、引き渡し
詳しくはこちらをご参照ください↓
⑥相見積もりと施工会社選びで初めて施工会社が決まる流れになります。
もちろん、最初から施工会社が決まっている場合はこれがなくなり、実施設計の物量も少なくて済むかもしれませんが…
設計事務所に注文住宅を頼む大きなメリットの一つである、相見積もりでの適正な建築費を割り出すことができなくなります。
基本設計とは
基本設計では配置図、平面図、立面図、断面図(矩計図)、建築模型、イメージパースなどを制作します。
これらを用いて、建築基準法上での規制などをチェックして建築のボリューム(建築の外観)を決めたり、間取りなどを確認します。
基本設計は建てる建築のコンセプトや方向づけなどに関わってくるため、
この段階でしっかりと設計しないと実施設計が途中で行き詰るなんてことがあります。
実施設計とは
実施設計では、基本設計で描いた図面の精度がより具体的になります。
描く図面は、配置図、平面図、立面図、断面図(矩計図)、各部詳細図、展開図、天井伏図、建具(サッシ)図、家具図、外構図、換気・照明・給排水衛生設備図、換気計算、照度分布図、構造図、構造計算などです。
この図面をもとに施工会社は見積もりを作ります。
現場が始まってからこの図面をもとに施工会社は施工図を作り建物を建築していきます。
各段階で決めるべきこと

設計事務所の注文住宅では、設計の各段階で施主が決めなければならないことがあります。
各段階とは、基本設計、実施設計、現場が始まってからの段階のことです。
それぞれに決めるべきことが異なるためにしっかりと理解しておきましょう。
基本設計で決めること
施主が基本設計で決めることは以下になります。
・建築のボリューム(建築の外観)
・間取り(平面図)
・建築のコンセプト
建築のボリューム(建築の外観)
建築のボリューム(建築の外観)は立面図や建築模型、外観パースなどで設計していきます。
建築基準法の高さ制限や道路斜線、隣地との距離による採光などを考慮してボリュームを検討していきます。
図面やCGではボリュームは分かりづらいので建築模型を作ってもらって検討した方がいいと思います。
この時には外壁や屋根などの素材をなににするのか(外壁:サイディング,左官,漆喰,羽目板、屋根:金属,瓦,スレートなど)を考えて一緒に決めていきましょう。
間取り(平面図)
間取り(平面図)は全ての基本になる大事な図面です。
自分が間取りに入って生活する時の動きをイメージして、家事動線が自分に合っているのかなど平面図で検討しましょう。
例えば、
買い物から帰って、荷物を置いて、キッチンに行く時に食品ストックできる収納が欲しい
食事の支度をして、食事を出す時は対面がいい
洗濯をして、洗濯物を干すところは近い方がいい
などをイメージして間取り(平面図)を決めましょう。
この時、内部の仕上げをなににするのかも一緒に考えておきましょう。
※内部の仕上げとは、床、壁、天井などの素材(無垢フローリング,タイル,CF,クロス,左官,羽目板など)のことです。
建物のコンセプト
建物のコンセプトは家族の意見がなかなかまとまらない時に方向性を定めてくれます。
コンセプトといっても難しいことではなく、わかりやすい言葉で明確にすることがおすすめです。
例えば
「老後も快適に暮らせる住まい」というコンセプトの場合
高齢になっても住みやすいように段差をなくしたり、手すりを設けたり、各部屋の温度差をなくしたりするなど
家のコンセプトに沿って設計が進めやすくなります。
実施設計で決めること
施主が実施設計で決めることは以下になります。
・仕上げの決定
・設備のグレードを決める
仕上げの決定
仕上げの決定とはメーカーのサンプルなどを取り寄せて一つずつ確認し決定する作業となります。
実施設計の段階で仕上げは一つずつ確認し決定していくのですが、この作業は時間のかかる作業になります。
メーカーのサンプルは小さいため、それを使用した場合の全体のイメージがつきずらいのでなかなか決めることができないなんてことがよくあります。
そんな場合は、3DCGパースなどを作ってもらったり、それを使用している実例やメーカーのショールームに実際に足を運ぶことがおすすめです。
設備のグレードを決める
設備のグレードを決める作業も実施設計の段階です。
メーカーのショールームに行って実物を見て使い勝手などを確認し決めていく作業になります。
メーカーのショールームに行くと自分が選んでいた設備にいろいろなオプションがあるのでなかなか決められないなんてことよくあります。
ショールームのコーディネーターはいろいろと進めてくるので、自分の使い勝手の基準をしっかりと持たなければ迷ってしまいます。
そんな場合は、気になるオプションは全部入れておき、見積り調整の段階で予算がオーバーしてしまったら削る作業をしましょう。
現場が始まってから決めること
施主が現場が始まってから決めることは以下になります。
・仕上げの確認
・納まりの確認
・予算の増減について
施主が決めることは実施設計の段階でほぼ終わっていますが、
実際に現場が進むとどうしてもうまく納まらないところが出てきます。
また、仕上げについては実際に施工してイメージしていたのと違ったなんてことがあります。
それらを施主に確認してもらい、変更するのかやそれに伴う工事予算の増減はどうするのかなどを決めてもらうことになります。
仕上げの確認
仕上げの確認とは実際に施工してみてイメージしていたのと一緒なのか違うのかを確認してもらうことです。
いくら実物のサンプルを見て選んでも、その場所の全体を施工してみないと分からないことはあります。
仕上げの変更は工事予算や工事期間に関わることなので、すぐに変更することはできませんが、可能な限り希望に沿った建築に近づけていきます。
納まりの確認
納まりの確認とは施工上どうしてもうまく納まらない箇所がある場合の代替案を確認してもらうことです。
代替案は設計事務所と施工会社、職人と現場で考えるのですが、それを最終的に決定するのは施主になります。
しっかりと現場でその納まりのその良し悪しを説明してもらいましょう。
建築の納まりは専門的な知識や経験がないとイメージしづらいのですが、実際の材料や現場でスケッチを描いてもらい決めていきましょう。
予算の増減について
予算の増減については仕上げや納まりの現場での変更に伴い出てきます。
現場監督は建築工事の予算の増減を把握し、なるべく安く早く綺麗に納める方法を現場で考えながら施工していきます。
それでも、追加工事で予算が増加してしまった場合はしっかりと話し合った上で施主の決定に委ねられます。
建築現場の予算は追加工事が発生することを想定して諸経費がとられれていますが、
相見積もりでそれを削り過ぎてしまうと工事費が増加した時に対応できなくなります。
予算に余裕のある現場ならいいのですが、現在ではなかなかそういう現場は少ないです。
また、追加工事がなくても材料を発注する段階で価格が上がってしまったなんてこともあります。
最近ではウッドショックなどがそれにあたります。
先に材料を押さえて発注を済ましておけば対応はできたのですが、
予算のない現場では現場が始まってからの発注になりがちになります。
しっかりと予算に余裕を持ち、諸経費はあまり削らないようにしましょう。
まとめ

今回は、設計事務所の注文住宅の設計の流れについてや、基本設計と実施設計でなにを決めるのかをご紹介してきました。
まとめると以下になります。
■基本設計とは
基本設計では配置図、平面図、立面図、断面図(矩計図)、建築模型、イメージパースなどを用いて、
建築基準法上での規制などをチェックして建築のボリューム(建築の外観)を決めたり、間取りなどを確認をする設計のこと。
■実施設計とは
基本設計で描いた図面の精度がより具体的になり、配置図、平面図、立面図、断面図(矩計図)、各部詳細図、展開図、天井伏図、建具(サッシ)図、家具図、外構図、換気・照明・給排水衛生設備図、換気計算、照度分布図、構造図、構造計算などを用いて、
施工会社は見積もりを作り、現場が始まってからこの図面をもとに建築していくための設計のこと。
建築のボリューム(建築の外観)
間取り(平面図)
建築のコンセプト
仕上げの決定
設備のグレードを決める
仕上げの確認
納まりの確認
予算の増減について
となります。
設計事務所の注文住宅では基本設計と実施設計のどちらも大切な設計です。
施工会社が決まっていたとしても、実施設計でのしっかりとした図面があるのとないのとでは、
現場が始まってからの工事の進み方がかなり違ってくると思います。
図面が揃っていない場合でも、施工図をしっかりと作るのであれば大丈夫ですが、工務店やハウスメーカーは施工図を作りたがらないと思います。
私の経験からですが、図面上で納まらないものは現場でも納まらないと思います。
設計事務所に注文住宅を頼むなら、実施設計まで頼みしっかりとした図面を描いてもらいましょう。
この記事で設計事務所の設計の流れでなにをすればいいのか分からないで不安に思っている人の悩みが少しでもなくなれば幸いです。
この記事が役に立った、面白かったという方はコメントしてくださいね。
また、FacebookやTwitterでみなさんのお役にたてる情報発信しています!
「いいね!」や「フォロー」していただけるとうれしいです。ヨロシク(b・ω・d)デス♪
アーキトリック一級建築士事務所